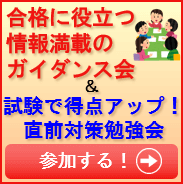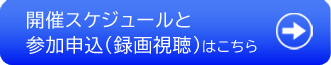遺言
遺言で指定できること
遺産の相続
各相続人の相続分、遺産分割方法を指定します。
遺産の遺贈
特定の人や団体に、無償で遺産を与えるその金額と方法を指定します。
遺産の寄付
特定の人や団体に、遺産を寄付することもできます。
寄付をした財産については、相続税の課税対象外として扱われます。
子供の認知
婚姻関係がない男女間で生まれた子は、「父親の認知」がなければ、相続人となることができません。
もしそのような子に財産を残すのであれば、まずこの「父親の認知」を遺言書に記載する必要があります。
この認知は、出生前の胎児にも行うことができます。
(ちなみに、上記の子の母親は、出産の事実があるため認知は不要です)
認知を行い、法的に子供とみなされれば、その子は非嫡出子として扱われます。
未成年後見人の指定
子が未成年である場合、その子を世話してくれることを期待できる人に、未成年後見人を指定することができます。
(FP技能士試験で出題される「成年後見制度」とは異なる制度です)
相続人の廃除、廃除の取消
相続の対象となる人を指定し、その人を相続人から廃除することを記載できます。
廃除の取り消しも、行うことができます。
遺産分割の禁止
2019年5月 FP技能士2級 学科 問54より
1.被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
この記述は適切です。
たとえば、遺産分割によって家業が継続できなくなる可能性がある場合や、遺産分割でもめることが予想される場合には、これらの問題を回避するために、遺産分割の禁止を遺言で定めることができます。
また、遺言ではなく、相続人全員の合意で遺産分割の禁止を行うことも可能です。
ちなみ実務上のワンポイントですが、遺言で遺産分割の禁止が指定されても、相続人全員で遺産分割内容の合意が取れれば、遺産分割を実行することは可能です。
実務上の知識として、知っておくとよいでしょう。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言内容の実現を行う者のことです。
特に、上記の認知と相続人の排除は、遺言執行者のみが執行できます。
一般的には、弁護士等の専門家が遺言執行者となります。
遺言書に記載しておくことで、信頼できる人に遺言の執行を依頼し、確実な遺言実行を期待できます。遺言で指定しなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言の証人(公正証書遺言、秘密証書遺言)
2014年1月 FP技能士2級 学科 問54より
(2015年1月 FP技能士2級 学科 問56も類題)
(2018年5月 FP技能士2級 実技(きんざい個人) 問13も類題)
2.公正証書遺言の作成時において、遺言者の配偶者が証人として立ち会うことはできない。
本選択肢は適切です。
以下に該当する人は、遺言の証人になることはできません。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者の相続人になれる立場の人・配偶者を含む)
- 推定相続人の配偶者、直系血族
- 受遺者(遺言により、遺贈などによって財産を貰える立場の人)
- 受遺者の配偶者、直系血族
- 公証人、公証人の配偶者、公証人の4親等内の親族
兄弟姉妹は、推定相続人でなければ、証人となることができます。
万一、証人になれない人を証人とした場合、遺言が無効となります。
FPは、遺言の証人になることができない上記の立場に該当しなければ、遺言の証人になることはできます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の署名と捺印
自筆証書遺言では、本人の署名と捺印が必要とされています。
氏名の記載にあたっては、芸名やペンネームで記載した場合も遺言は有効となります。要するに、遺言を書いた人がしっかり特定されればよいということですが、やはり本名で書いたほうが無難です。
捺印はその形式は定められておらず、実印でなくても認印、または拇印であっても有効と考えられています。ただ、「本人の意思」を強く証明するためには、実印を用いたほうがよいでしょう。
自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。
検認しなかったとしても、遺言書の効力がなくなることはなく、遺言の内容は有効のままです。
しかし、検認しなかった場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
公正証書遺言
遺言の秘匿性
2012年5月 FP技能士2級 学科 問53より
■選択肢
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、普通遺言方式のうち、内容の秘匿性が最も高い方式である。
■解説
この選択肢は不適切です。公正証書遺言の場合、遺言内容は公証人と二人の証人に開示されます。一方、秘密証書遺言は、公証人と二人の証人が遺言の存在を認知はするものの、その内容は開示されません。そのため、公正証書遺言より秘密証書遺言の方が秘匿性は高く、公正証書遺言が最も秘匿性が高いとはいえません。
公正証書遺言の破棄
2012年5月 FP技能士2級 学科 問53より
■選択肢
公正証書遺言は、遺言者が遺言書の正本の一部を破棄した場合には、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。
■解説
この選択肢は不適切です。一般に、遺言を破棄すれば、その部分について遺言を撤回したことになります。しかし公正証書遺言の場合は注意が必要です。
公正証書遺言の原本は公証役場に存在するため、遺言者の手元にある正本の一部を破棄しただけでは正式な破棄とはみなされません。公正証書遺言の内容を一部破棄したい場合には、新たな遺言を作成する、遺言で指定した財産を生前に処分する、などの方法を取らなくてはなりません。
公正証書遺言への署名捺印
2015年9月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産) 問14より
1.公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を聞きとり、公証人が作成するため、小山さん自身が署名・押印をする必要はない。
この記述は不適切です。
公正証書遺言の内容自体は公証人に対して口述するため、公正証書の本文を書くのは公証人が行います。
ただし、公証人が作成した遺言書に対して、最後に依頼者自身が署名、捺印をする必要があります。
ちなみに、公正証書遺言には実印と印鑑証明書が必要です。
「公正証書遺言は、依頼者がまったく何も書かなくてよい、押印も必要ない」という考え方は誤りです。細かい点ですが、自筆証書遺言との違う点、同じ点についても確認しておきましょう。
公正証書遺言の年間作成件数
2018年1月 FP技能士2級 学科 問60より
3.日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの10年間にわたり、減少が続いていた。
この記述は不適切です。この10年間で、公正証書遺言の件数は増加傾向で推移しています。
詳しくは、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。
公証人に対する手数料
2019年5月 FP技能士3級 実技(きんざい保険)問13より
3) 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」
この記述は不適切です。
公正証書を公証人が作成する場合の手数料は有料であること、またその手数料の額まで、法令で決まっています。
その金額は、全国どの公証役場でも同じです。
詳しくは下記URLでご覧いただけます。興味ある方は、一度ご覧下さいね。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12
遺言の押印
2014年1月 FP技能士2級 学科 問54より
1 .自筆証書遺言は 、遺言者がその全文 、日付および氏名を自書し 、押印することによって成立するが、印鑑登録された実印で押印しなければ遺言書自体が無効となる。
本選択肢は不適切です。
自筆証書遺言では、実印に限らず、認印でも問題ありません。ただし本人の意思を強く証明するという点では、実印の方が望ましいと言えます。
ちなみに、公正証書遺言への押印は、遺言者の実印が必要です。
秘密証書遺言の場合は、自筆証書遺言の場合と同じく認印でも構いません。
遺言書の再作成・撤回
2014年1月 FP技能士2級 学科 問54より
4.遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合は、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であっても、公正証書遺言の内容が優先して有効とされる。
本選択肢は不適切です。これは過去に何度も出題されている内容ですね。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の種類に関係なく、後の日付で作成された遺言が優先されます。従って、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することは可能です。
遺言書を書き直すと、新しい遺言書が有効となります。
遺言の内容を変更したい場合には、新しい遺言を書きます。
古い遺言書と新しい遺言書の内容に違いがある場合には、古い遺言書の内容は無効となり、新しい遺言書に記載の内容が有効となります。
古い遺言書に書いてあるのに、新しい遺言書に記載がない事項については、内容を取り消したとみなされる場合があります。
そのため、遺言書を書き直す場合には、変更内容の差分だけを書くのではなく、全文を書き直すようにした方が実務上は望ましいです。
遺留分を侵害した内容の遺言
遺言に、遺留分を侵害する内容の遺産分割方法を書いても、その遺言の内容は無効にはなりません。
ただし、遺留分の権利がある者が減殺請求権を行使した場合には、結果的に遺言通りの遺産分割にならなくなります。
- FP技能士3級と2級の過去問から、難問(試験対策テキストには記述がない問題、多くの人が間違えやすい問題など)を中心に解説しています。
正解だけでなく、問題の背景や周辺知識も含めて解説しています。 - 万一記述に誤りがあると思われた方は、お問い合わせページよりお知らせください。正しい内容をお知らせし、当サイトも訂正します。
(法改正により、すでに古い記述となっている場合があります) - 調べたい単語で検索できる、検索ページはこちら。
メールマガジンもご登録下さい。受験案内、試験勉強のコツ、過去問解説、今後の勉強会の開催案内、その他FP試験の合格に役立つ情報をたくさんお届けしています!
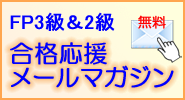
FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!
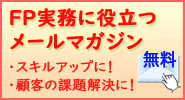
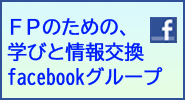
過去問の無料解説サイトのご案内
FP3級と2級の試験問題を、無料で解説してくれているサイトのご紹介です。
- 目指せ一発合格!2級FP過去問解説
- 目指せ一発合格!3級FP過去問解説
学科試験はもちろん、全種類の実技試験まで網羅。
過去問での徹底学習を、無料で行いたい方は、ぜひご活用ください!