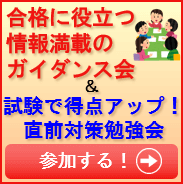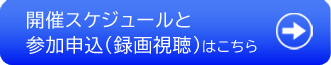<注意>
- 本ページに記載の所得税率は、すべて復興特別所得税は考慮していません。
2022年9月試験より反映される内容
原則として、2022年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
雑所得における取引等関係書類の保管
改正前:
取引関係書類の保管は、規定されていなかった。
改正後:
前々年分の雑所得に係る収入金額が300万円超の場合は、取引関係書類を5年間保存することが義務付けられる。
前々年分の雑所得に係る収入金額が1000万円超である場合は、取引関係書類を、確定申告書に添付する必要がある。
※この改正内容は、2022年度の確定申告(2023年1月〜3月の申告)から適用されます。
2022年1月試験より反映される内容
原則として、2021年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
成年の年齢変更
次の内容について、これまで「20歳」だったものが「18歳」へと変更になります。
- NISA口座を開設できるのは、口座開設する年の1月1日時点において、18歳以上の者である。
- つみたてNISA口座を開設できるのは、口座開設する年の1月1日時点において、18歳以上の者である。
- ジュニアNISA口座を開設できるのは、口座開設する年の1月1日時点において、18歳未満の者である。
- 相続税の未成年者控除は、その対象となる相続人が18歳未満の場合に適用できる。
- 相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件は、贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上の者である。
- 贈与税において、直系尊属からの贈与によって特定税率が適用されるのは、受贈者が 贈与の年の1月1日時点において18歳以上の場合である。
- 上場株式における贈与税の納税猶予の適用を受ける場合において、受贈者の年齢要件は、贈与の時点において18歳以上の者である。
- 人事業者に対する事業用資産の贈与税の納税猶予制度を利用する場合において、受贈者の年齢要件は、贈与の時点において18歳以上の者である。
その他
- 女性が婚姻できる年齢が、16歳以上から18歳以上へと引き上げ
※この改正内容は、2022年4月以降に適用されますが、FP試験での注目が高いため、子の試験から出題される可能性があります。
2021年9月試験より反映される内容
原則として、2021年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
国外中古建物の損益通算
改正前:
不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損益通算の対象にすることができる。
改正後:
不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損益通算の対象にすることはできない。
※この改正内容は、2021年1月1日以後に、従前住宅の譲渡をした場合に適用されます。
消費税の申告期限
改正前:
消費税の確定申告書の提出期限は、事業年度終了後2カ月です。
改正後:
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けていることを前提に、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長でき、事業年度終了後3カ月以内に提出できます。
※この改正内容は、2021年4月以後に終了する事業年度の課税期間 から適用されます。
2020年9月試験より反映される内容
原則として、2020年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
健康保険の被扶養者要件
改正前:
被扶養者として認められる要件に、国内に居住する要件は存在しなかった。
改正後:
被扶養者として認められる要件に、「原則として国内に居住している者」が追加された。具体的には、住民基本台帳に住民登録されている(住民票がある)かどうかで判定します。
なお、海外留学や転勤に同行するなどの条件を満たす場合には、改正前と同様に被扶養者として認められます。
※この改正内容は、2020年4月以後に適用されます。
65歳以上の雇用保険料
改正前:
65歳以上の雇用保険の被保険者について、雇用保険料は免除される。
改正後:
65歳以上の雇用保険の被保険者について、雇用保険料は免除されず支払う必要がある。
※この改正内容は、2020年4月以後に適用されます。
フラット35
改正後:
総返済負担率の「年間収入÷借入額」の算式の借入額に、賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金の返済額も含めることとなります。
※この改正内容は、2020年4月以後に適用されます。
寡婦控除・寡夫控除
改正前:
未婚の者は、寡婦控除も寡夫控除も受けられなかった。
寡婦は、所得金額が500万円以上であっても寡婦控除を受けられた。
寡夫の場合の控除額は、寡婦の場合より低い控除額であった。
改正後:
未婚で生計一の子がいる場合は、寡婦控除または寡夫控除を受けられる。
寡婦は、所得金額が500万円以上の場合、寡婦控除を受けられない。
寡夫の場合の控除額が、寡婦の場合と同額になった。
※この改正内容は、2020年度の確定申告(2021年1月〜3月の申告)から適用されます。
住宅ローン控除
改正前:
新規住宅の居住の用に供した日の属する年から3年目の年に従前住宅を譲渡した場合、従前住宅に対する居住用財産の3000万円の特別控除の特例と、新規住宅における住宅ローン控除は、併用して適用を受けられる。
改正後:
上記場合に、居住用財産の3000万円の特別控除の特例の適用と、新規住宅における住宅ローン控除の適用とは、いずれか一方のみ選択適用となる。
※この改正内容は、2020年4月1日以後に、従前住宅の譲渡をした場合に適用されます。
取得価格30万円未満の資産の一括償却の特例
改正前:
法人税法上の中小法人に該当していれば、適用を受けられた。
改正後:
法人税法上の中小法人に該当していても、常時使用する従業員の数が500人超の法人はその適用を受けることはできない。
※この改正内容は、2020年4月1日以後に適用されます。
交際費の損金算入
接待飲食費の額の50%を交際費として損金算入できる制度に関して。
改正前:
資本金の額に関係なく、適用を受けられます。
改正後:
資本金の額等が100億円を超える法人は、この適用を受けることはできません。
※この改正内容は、2020年4月1日以後に適用されます。
不動産取引の契約不適合責任
改正前:
売主は、買主が知らなかった瑕疵(隠れたる瑕疵)について責任を負う
改正後:
売主は、買主が知っていた瑕疵を含め、契約で定められた取引に適合しないものについて責任を負う。ただし責任を負わない特約は可能。
改正前:
瑕疵があった場合、買主は契約解除または損害賠償請求を行える。
改正後:
契約不適合があった場合、買主は契約解除または損害賠償請求が行えるほかに、追完請求と代金減額請求を行うことができる。
契約締結のあと引渡の時までに、対象となる不動産が売主と買主の双方に責任がない事象によって滅失した場合について、
改正前:
買主は代金を支払う義務がある。
改正後:
契約は自動的に解約とはならないが、買主は代金の支払いを拒むことができる。
※以上の改正内容は、2020年4月以降に適用されます。
不動産の固定資産税
改正前:
固定資産税は不動産登記上の所有者に課税されるため、登記上の所有者を特定できない場合は、誰にも固定資産税は課税されない。
改正後:
登記上の所有者を特定できない場合であっても、不動産を使用している者がいる場合、市町村長は条例により、当該使用者に対して固定資産税の課税に必要となる氏名、住所等の必要事項を申告させることができる。
また、一定の調査を尽くしても当該不動産の所有者を一人も明らかにできなかった場合には、その使用者に対して固定資産税を課税することができる。
※この改正内容は、2020年4月以降に適用されます。
民法改正(法人の債務の保証)
改正後:
法人が資金を貸付けにより調達する場合において、その債務の保証人が該当法人の経営者でない場合は、公正証書によって該当保証人が保証債務を履行する意思を表示しなければ、その保証債務の効力は生じない。
※この改正内容は、2020年4月以降に適用されます。
配偶者居住権
改正後:
被相続人の死亡後も、被相続人と同居していた配偶者が引き続き自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が導入される。
被相続人が居住していた自宅建物が配偶者を含めて遺産分割の対象となる場合、被相続人の配偶者は、相続発生後6カ月間または遺産分割が確定するまでのいずれか遅いほうの時まで、当該自宅建物に居住する権利(配偶者短期居住権)を有する。
2020年1月試験より反映される内容
原則として、2019年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
特定一般教育訓練給付金
2019年10月より、特定一般教育訓練給付金の制度が開始されます。
通常の一般教育訓練給付金より、高度な教育訓練にあたる講座を受講修了した場合に対象となります。
教育訓練経費の4割(上限20万円)が支給されます。
年金生活者支援給付金
2019年10月より支給開始されます。
- 65歳以降の老齢年金受給者で、その受給金額が老齢基礎年金満額相当額に満たない場合には、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
- 65歳以降の老齢年金受給者で、その受給金額が老齢基礎年金満額相当額を超え、「老齢基礎年金満額相当額+10万円」に満たない場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
- 障害基礎年金受給者には、障害年金生活者支援給付金が支給されます。
- 遺族基礎年金受給者には、遺族年金生活者支援給付金が支給されます。
以上4種類の支援給付金は、すべて非課税です。
フラット35
改正前:
借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限は、1億円である。
改正後:
借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限は、撤廃された(1億円以上でも可能)
フラット35の地域活性化型において、これまでの「空き家活用」以外に、「防災対策」と「地方移住支援」が新設された。
※この改正内容は、2019年10月以後に適用されます。
法人保険の経理処理
改正後:
定期保険と第三分野の保険は、最高解約返戻率によって次の4区分で経理処理をおこなうことになる。
・最高解約返戻率が50%以下の場合
・最高解約返戻率が50%超70%以下の場合
・最高解約返戻率が70%超85%以下の場合
・最高解約返戻率が85%超の場合
※この改正内容は、2019年10月8日以降に法人が契約する保険に適用されます。
上場有価証券の受け渡し日
改正前:
取引所に上場している株式、ETF等の有価証券の取引において、有価証券や売買代金の受渡日は、約定日から起算して4営業日後となる。
改正後:
取引所に上場している株式、ETF等の有価証券の取引において、有価証券や売買代金の受渡日は、約定日から起算して3営業日後となる。
※この改正内容は、2019年7月16日以後の売買より適用されます。
給与所得控除の改正
改正前:
給与所得控除額の上限は、220万円です(給与収入1000万円超)。
改正後:
給与所得控除の額を、従来より一律10万円引き下げます。
そのうえで、 給与所得控除額の上限が195万円になります(給与収入850万円超)。
※この改正内容は、2020年度の所得税より適用されます(2018年1月1日以後に生じる所得から適用対象)。住民税は2021年度より適用されます。
FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題される可能性があります。
公的年金等控除の改正
改正前:
所得の金額に関係なく、既定の公的年金等控除を受けられます。
改正後:
- 公的年金等控除の額を、従来より一律10万円引き下げます。
そのうえで、公的年金等控除額の上限が195.5万円になります。 - 公的年金等雑所得以外の所得の合計額が1000万円超の場合は、上記1の公的年金等控除額から、さらに10万円引き下げます。
- 公的年金等雑所得以外の所得の合計額が2000万円超の場合は、上記1の公的年金等控除額から、さらに20万円引き下げます。
※この改正内容は、2020年度の所得税より適用されます(2018年1月1日以後に生じる所得から適用対象)。住民税は2021年度より適用されます。
FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題される可能性があります。
基礎控除の改正
改正前:
どの納税者も、所得税では38万円、住民税では33万円の控除額です。
改正後:
基礎控除額を、従来より一律10万円引き上げ、所得税では48万円、住民税では43万円となります。
ただし、合計所得金額が2400万円を超えると段階的に基礎控除の額が下がり、2500万円を超えると基礎控除額は0円となります。
※この改正内容は、2020年度の所得税より適用されます(2018年1月1日以後に生じる所得から適用対象)。住民税は2021年度より適用されます。
FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題される可能性があります。
青色申告特別控除額の改正
改正前:
原則は10万円、ただし取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合は65万円です。
改正後:
原則は10万円のまま、取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合は55万円に引き下げられます。
ただし、正規の簿記の原則に従って記録をし、さらに電子帳簿保存または電子申告(e-Tax)のいずれかを行う場合には、控除額は65万円となります。
※この改正内容は、2020年度の所得税より適用されます(2018年1月1日以後に生じる所得から適用対象)。住民税は2021年度より適用されます。
FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題される可能性があります。
配偶者控除など人的控除の要件
改正前:
配偶者控除の適用要件:配偶者の合計所得額が38万円
配偶者特別控除の適用要件:配偶者の合計所得額が38万円超123万円以下
扶養控除の適用要件:扶養親族の合計所得額が38万円
改正後:
配偶者控除の適用要件:配偶者の合計所得額が48万円
配偶者特別控除の適用要件:配偶者の合計所得額が48万円超133万円以下
扶養控除の適用要件:扶養親族の合計所得額が48万円
※この改正内容は、2020年度の所得税より適用されます(2018年1月1日以後に生じる所得から適用対象)。住民税は2021年度より適用されます。
FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題される可能性があります。
住宅ローン控除
改正前:
住宅ローン控除の控除期間は、最大で10年です。
改正後:
消費税10%で購入した場合は、住宅ローン控除の控除期間は、最大で13年になります。
11年目以降は、住宅ローンの年末残高の1%と、税抜き建物価格×2%÷3のいずれか小さい金額が、住宅ローン控除の控除額となります。
※この改正内容は、2019年10月1日以後に取得する不動産に適用されます。
ふるさと納税
改正前:
全ての市町村と都道府県が、ふるさと納税の対象(2000円の自己負担で返礼品がもらえる)
改正後:
総務大臣が指定した市町村と都道府県に対してのみ、ふるさと納税の対象となる。
その指定の基準は、下記の2つです。
- 返礼品の返礼割合を3割以下にすること
- 返礼品を地場産品にすること
※この改正内容は、2019年6月1日より適用されます。
消費税率の改正
改正前:
税率は8%
改正後:
税率は原則10%だが、一定条件を満たす食料品と定期購読新聞は、軽減税率として税率は8%
※この改正内容は、2019年10月1日より適用されます。
住まい給付金
改正前:
住まい給付金の額は、最大で30万円である。
改正後:
消費税率10%の適用により住宅を取得した場合は、最大で50万円が給付される。
※この改正内容は、2019年10月1日より適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例1
改正前:
受贈者が30歳になるまでの間になされた贈与は、非課税の対象となります。
改正後:
受贈者が23歳未満のときになされた贈与は、非課税の対象となります。
受贈者が23歳以上のときになされた贈与のうち、学校等以外に支払われる教育費は、原則として非課税の対象外となります。ただし例外的に、教育訓練給付金の支給対象となる講座の受講費用は、非課税の対象となります。
※この改正内容は、2019年7月1日以後の贈与に対して適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例2
改正前:
受贈者が30歳に到達した場合、その時点の教育資金の残高に対して贈与税が課税されます。
改正後:
受贈者が30歳に到達しても、以下のいずれかに該当する場合は、贈与税が課税されません(ただし40歳に到達したら、必ず贈与税が課税されます)
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
- 学校等に在学している
※この改正内容は、2019年7月1日以後の贈与に対して適用されます。
特別寄与料
改正前:
被相続人の生前に、相続人でない親族が被相続人の療養看護を行うなどをしたことで、被相続人の財産の維持や増加に対して特別な寄与を行っても、相続人に対して金銭の支払いを請求することはできない。
改正後:
被相続人の生前に、相続人でない親族が被相続人の療養看護を行うなどをしたことで、被相続人の財産の維持や増加に対して特別な寄与を行っても、相続人に対して金銭の支払いを請求することはできる。これを特別寄与料という。
※この改正内容は、2019年7月1日以後の相続に対して適用されます。
被相続人の預金口座からの払い戻し(新設)
被相続人の相続発生後に、各相続人は被相続人の名義の預貯金口座に対して、「預貯金債権の額×1/3×各相続人の法定相続割合」までを、他の相続人の同意を必要とせず払い戻しをすることができる。ただし払い戻せる金額は、同一の金融機関につき、150万円までが限度である。
※この改正内容は、2019年7月1日以後の相続に対して適用されます。
遺留分減殺額請求
改正前:
相続人が遺留分を侵害された場合、他の相続人に対して遺留分の請求を行うと、その財産は遺留分請求者との共有財産となる(遺留分減殺請求という)
改正後:
相続人が遺留分を侵害された場合、他の相続人に対して遺留分の請求を行うと、その財産は共有財産とはならず、金銭による請求となる(遺留分減殺額請求という)
※この改正内容は、2019年7月1日以後の相続に対して適用されます。
2019年9月試験より反映される内容
原則として、2019年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
国民健康保険で産前産後期間に保険料を免除
改正前:
国民年金第1号被保険者は、産前産後期間中も国民年金保険料を納付しなければならない。
改正後:
国民年金第1号被保険者は、産前産後期間中は国民年金保険料が免除される。この免除期間は、基礎年金受給額の計算において、保険料を納付したものとみなす。
※この改正内容は、2018年4月1日以降に適用されます。
休眠預金の取り扱い
2019年1月1日以降、過去10年以上取引の無い預金等は、休眠預金等として取り扱われ、その預金は預金保険機構に移管されます。
休眠預金として移管後も、預金者本人は本人確認を経て、引き出すことはできます。
国際観光旅客税
日本から国外に出国する場合、出国1回につき1000円の国際観光旅客税を支払う必要があります。
※この改正内容は、2019年1月7日以後の出国に適用されます。
法人税率
2019年4月以降も、引き続き下記の法人税率が適用されます。
| 所得が 800万円以下 |
所得が 800万円超 |
|
|---|---|---|
| 大法人 | 23.4% | 23.4% |
| 中小法人 | 15% | 23.4% |
空き家に係る譲渡所得の特別控除
改正前:
被相続人が老人ホームに入所していた場合、本特別控除の適用を受けられません。
改正後:
被相続人が老人ホームに入所していた場合、要介護認定を受けていれば、本特別控除の適用を受けられます。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の譲渡に対して適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例1
改正前:
贈与者が死亡した場合、その死亡時点での残高は、被相続人の相続財産には加算しません。
改正後:
贈与者が死亡した時点において、以下のいずれかに該当する場合は被相続人の相続財産には加算しません(逆に、いずれにも該当しなければ、相続財産に加算します)
- 受贈者が23歳未満である
- 受贈者が学校等に在学している
- 受贈者が、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例2
改正前:
受贈者の所得要件はありません。
改正後:
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は、本特例の適用を受けられません。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例2
改正前:
受贈者の所得要件はありません。
改正後:
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は、本特例の適用を受けられません。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
遺言の財産目録の様式
改正前:
遺言全文(財産目録を含む)は、手書きによる直筆でなければならず、パソコン等で作成したものは無効となる。
改正後:
遺言本文の中の財産目録については、所定の要件を満たせばパソコン等での作成が認められるようになる。
財産目録以外の記述については、パソコン等で作成した場合は無効となる。
※この改正内容は、2019年1月13日以後に書かれた遺言に対して適用される。
小規模宅地の特例(事業用)
改正前:
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地も、小規模宅地の特例の適用を受けられます。
改正後:
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地は、原則として小規模宅地の特例の適用を受けられません。
ただし下記の要件をすべて満たしている場合は、特例の適用を受けられます。
- その宅地上で、事業の用に供されている減価償却資産がある
- その減価償却資産の価額が、当該宅地の価額の15%以上である
※この改正内容は、2019年4月1日以後に発生する相続に対して適用される。
個人事業者への事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予
2019年1月より、個人事業主が事業用資産を相続または贈与で取得した場合に、一定要件のもと、その事業用資産に対応する相続税や贈与税の税額が猶予されます。
被相続人の事業の用に供されていた土地は、その面積のうち400m2を上限に、建物は床面積のうち800m2を上限として納税猶予の対象となります。
この納税猶予の対象となった土地は、小規模宅地の特例の適用を受けることはできません(併用は不可)
また、被相続人と相続人が、ともに青色申告の承認を受けている必要があります。
以下に挙げる点は、非上場株式の納税猶予と同じものとなっています。
- この納税猶予の適用を受けるためには、特例継承計画を作成し、都道府県知事の確認と認定を受けなければならない
- 贈与税の納税猶予から、相続税の納税猶予へ移行できる
- 猶予の取り消しとなった場合は、猶予された税額に加えて、利子税の納付が必要
メールマガジンもご登録下さい。受験案内、試験勉強のコツ、過去問解説、今後の勉強会の開催案内、その他FP試験の合格に役立つ情報をたくさんお届けしています!
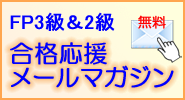
FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!
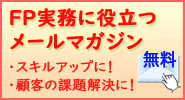
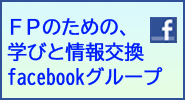
過去問の無料解説サイトのご案内
FP3級と2級の試験問題を、無料で解説してくれているサイトのご紹介です。
- 目指せ一発合格!2級FP過去問解説
- 目指せ一発合格!3級FP過去問解説
学科試験はもちろん、全種類の実技試験まで網羅。
過去問での徹底学習を、無料で行いたい方は、ぜひご活用ください!